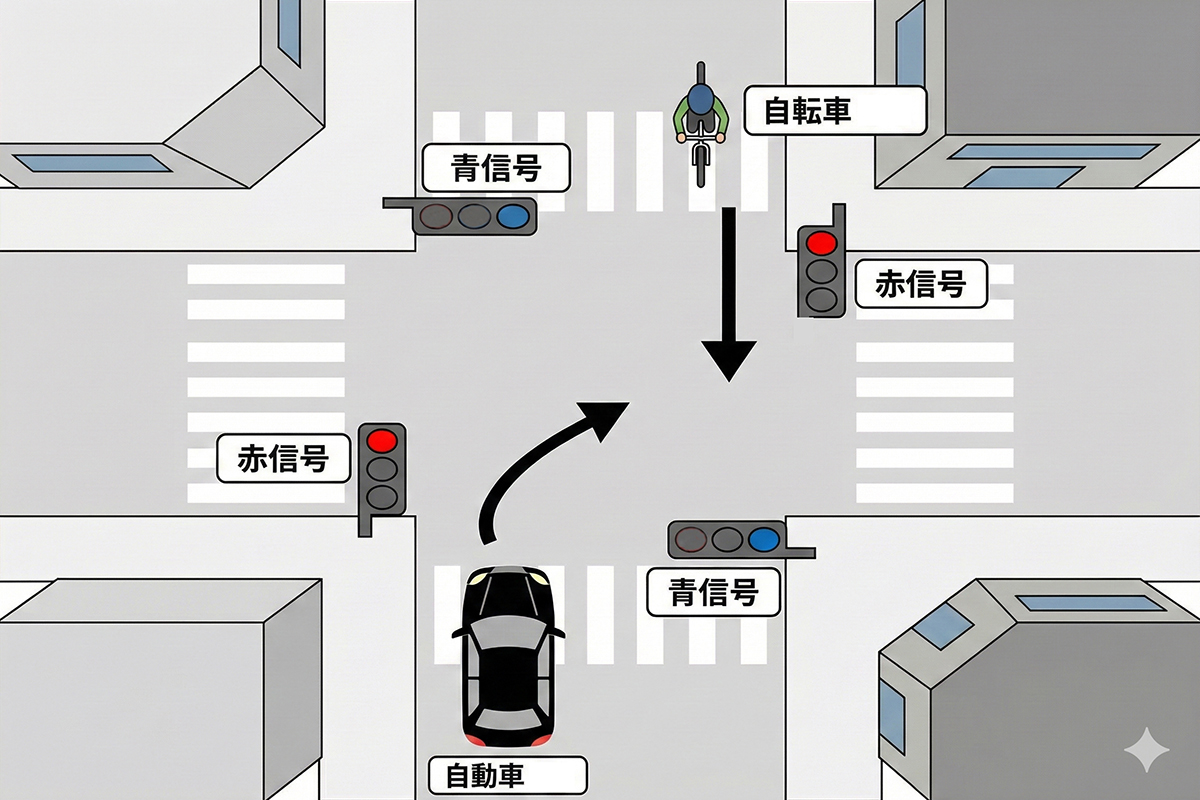不屈の精神で東京五輪ロードレースへ出場、宇都宮ブリッツェン・増田成幸の自転車人生

―自転車にハマったきっかけを教えてください
中学3年生か高校1年生のとき、フジテレビで放送されていたツール・ド・フランスの総集編を観て、ロードレースを知り、自転車競技をしてみたいと思いました。その後、高校2年生の春にロードバイクを買いました。小さい頃からお年玉で貯めていた貯金を使いました。16万円くらいだったと思います。自分の貯金でギリギリ買えました。
ロードバイクを購入してから、自転車競技部を作ろうとしましたが、学校から許可が下りず、自転車競技部がある他の高校の練習に参加していました。休日はお世話になっていた自転車店のクラブチームの方々と練習をしたりしながら走っていました。
学校の部活に所属していませんでしたが、高校3年生の夏に全国高等学校総合体育大会(インターハイ)に出場したくて、全国高等学校体育連盟の本部がある学校の先生に「どうしても出場したいのですが駄目ですか?」と電話で直談判をしました。当時から顔は知っていてもらっていたので、善処してくれたのだと思います。「よしわかった。ただ、勝ち上がってもインターハイなどには出られないけどいいか?」と言われましたが、予選に出場させてもらいました。黒いレーサーパンツと、白地のジャージで出場しました。ジャージには、名前と学校名を書いたゼッケンを親に着けてもらったのを覚えています。
―高校卒業後に一度、競技に区切りをつけたんですよね?
大学受験で自転車を休んでいた時期もありましたが、大学入学後、鳥人間コンテストに出場する航空研究会に入りました。鳥人間コンテストは、人力飛行機の滞空時間と飛行距離を競う大会です。サークルでは人力飛行機のパイロットになり、トレーニングのために、ロードバイクをひっぱり出して、再び乗り始めました。

―なぜ、航空研究会に入りましたか?
大学生になったら学業以外にも、熱くなれるものが欲しいと思い、それで見つけたのが、航空研究会でした。航空研究会は理工学部の中では花形のサークルでしたが、時間的にも体力的にもきついのです。
授業終了後はすぐにサークルに行かなければならず、徹夜の作業もありました。もちろんバイトもできません。人力飛行機ができると、春は毎週末、試験飛行に行くのですが、それもハードでした。深夜1時に大学に集合して、現地で人力飛行機を組み立て、風待ちをして日の出とともにフライトをして、昼前に帰ってきて、疲れて果てて寝てしまい1日を終えるという感じです(笑)。
1年生のときは、自分たちの飛行機を作っているわけではなく、「どうしてこんなことをやっているのだろう?」と思うほどです。しかし、続けていくうちに仲間との友情や絆が芽生えて、楽しくなっていきました。サークルも仕事も結局、人間関係がすべてですよね。四六時中一緒にいて泣いたり感動したり、喜びをわかちあったり、達成感を共有したり。大学に通って一番良かったのは、かけがえのない宝物といえる友人11人に巡りあえたことです。今も同期とは頻繁に連絡を取り合っています。一生の友人です。
そうした大学生活を送り、航空研究会は3年生の夏に引退する予定だったのですが、鳥人間コンテストが台風で中止になってしまい、引退できませんでした。大学4年生のときに日本記録に挑戦して達成することができました。
―その後はどうなりましたか?
実は大学に6年通ったのですが、大学3年生の頃から本気でプロロード選手になりたいと思っていました。大学1、2年生のときは「自分はエンジニアになるのだろう」と思って勉強をしていましたが、やはりプロロードレーサーになりたいと考えるようになったのです。ただ、卒業だけはしようと思いました。
転機になったのは、大学4年生のときです。ジャパンカップサイクルロードレースのオープンレースで2位になって、当時、栗村修さんが監督を務めていたチーム(当時はミヤタスバルレーシングチーム、翌年にチームミヤタに改称)から声をかけてもらいました。大学生活もやりくりできそうでしたので、大学5年生、6年生はそこで走っていました。5年生のときは、初年度で学生選手ということもあり、機材もウェアも補給食も遠征費も全部支給してもらえましたので、非常に嬉しかったことを覚えています。

―その後、チームは解散します
2007年に浅田顕さんが監督を務めるエキップアサダに入りました。当時は、新城幸也選手(現バーレーン・ヴィクトリアス所属)や中島康晴選手(現キナンサイクリングチーム所属)、宮澤崇史さん、福島晋一さん、福島康司さん、清水都貴さん、岡崎和也さん、菊池誠晃さんといったメンバーがいました。
エキップアサダでは、ツール・ド・北海道で宮澤崇史さんの総合優勝をアシストしましたが、目立った成績は残せませんでした。そこそこ強い若手の選手といった感じだったのではないでしょうか。その後、チーム解散に伴い、チームNIPPOに移籍し、イタリアに行き、良い経験を積むことができました。
―2011年に宇都宮ブリッツェンに加入、その後2013年には海外チームに移籍されました
2010年10月に、人力飛行機に挑戦して背骨を折る大ケガをしてしまいました。チームNIPPOのサテライトチームで国内で走るという選択肢もありましたが、当時、宇都宮ブリッツェンの監督だった、栗村修さんに誘っていただき、宇都宮ブリッツェンに加入することになりました。栗村さんは以前から熱心に声を掛けてくださっていました。
2011、2012年は日本で活動し、海外チームへの移籍の話もいただきました。海外で走りたいと思っていたので、即決でした。ただ、行ってみると、肉体的にも精神的にもストレスがありました。いくつかレースに出場しましたが、身体を壊して前半はあまり走れませんでした。その年の全日本選手権で3位に入り、その後の秋のレースは調子良く走れました。
―その後、宇都宮ブリッツェンに再加入されます。2013年に東京五輪の開催が決まりましたが、意識はしていましたか?
当時はまったく意識していませんでした。ただ、ケガのリハビリでJISS(国立スポーツ科学センター)のお世話になった際、別の種目のスポーツ選手はみな五輪を目指していました。彼らに影響を受けて、五輪出場への思いが芽生えました。本気で意識したのは、2016年のリオ五輪が終わった瞬間です。4年後の東京のオリンピックに向けて全身全霊を捧げようという気持ちになりました。
―五輪出場を目指すなかで、一番大変だったことは?
バセドウ病を患ったときが一番辛かったです。2017年4月にバセドウ病と診断されてしまいました。五輪に向けては、代表選考のときにピークを迎えられるよう、日々の積み重ねが重要になります。そのために、2017、2018年はたゆまぬ努力を続ける必要があるわけですが、蒔いた種に水をやれない状態が続いていました。バセドウ病は、「一年ぐらいかければ多分よくなるよ」という感じなので、出口の見えないトンネルの中をさまいながら、トボトボ歩き続ける気分です。

バセドウ病と診断されてから、最初の1カ月は家からも全然出られませんでした。就寝時も心臓がドキドキするので、治療をしなければ、死んでしまうと思いました。心臓がドキドキする危なさは経験したことのある人にしかわからないと思います。
当初は自転車にも乗れませんでしたが、徐々にママチャリ(軽快車)に乗って、スーパーに行けるようになりました。そこから、1日30分のロードバイクのトレーニングを始めて、徐々に距離や時間を伸ばしていきました。しかし、当時は何カ月も薬で抑え込む治療をしていたので、波があって辛かったです。復帰しても、走れないときもあり、全然ダメでした。
辛いときは孤独ですね。家族は支えにも癒しにもなってくれました。最周囲のサポートにも導かれて、復帰できたので感謝しています。
―増田選手の不屈の精神はどこから来たものですか?
挫折を味わっても、とりあえず続けてみることで、花開くことがあります。そうした経験が1回ではなく2回、3回とあったからですかね。
何度か大怪我をしましたが、そのたびに自転車に乗れないからと、何もせずに諦めていたわけではありません。自分の場合、ウエイトトレーニングやリハビリを繰り返した結果、ものすごく強くなれました。周囲のサポートがあり、導かれて復帰できたので感謝しています。
ただ、困難なことがあったとき、辞めたくて辞めるなら別ですが、やりたい気持ちを残したまま辞めるのは絶対に止めるべきです。自分が今、成長できているのかどうかわからないときも、やり続けていれば1ミリでも前に進んでいるのだと思います。

―自転車業界の盛り上がりはどう感じていますか? 海外のようにたくさんのレースが日常的に開催されるなど、文化的なところも含めてどう感じていますか?
あらゆる面で環境が変わったらと思っています。文化は一日にしてはならないので、少しずつ根付いていけば、と思います。ちなみに、宇都宮ブリッツェンの堀孝明選手はジャパンカップサイクルロードレースがきっかけで自転車競技を始めた珍しいタイプの選手です。素敵な動機ですよね。
いきなり本場のヨーロッパみたいな盛り上がりは難しいですが、それでも、自分が高校生のときと比べると、今は身近にレースが開催されるようになったと感じています。
―増田選手の今後の目標は?
明確なビジョンはありませんが、「まだ、辞められない」という思いで、今年も選手活動を続けています。チームの中ではまだ一番強く、選手を辞めるために、若手を育てたいです。一緒にトレーニングをするなど、チームメイト全員のサポートができているわけではありませんが、やる気のある若手、求むという感じです。
取材日: 2022年2月10日