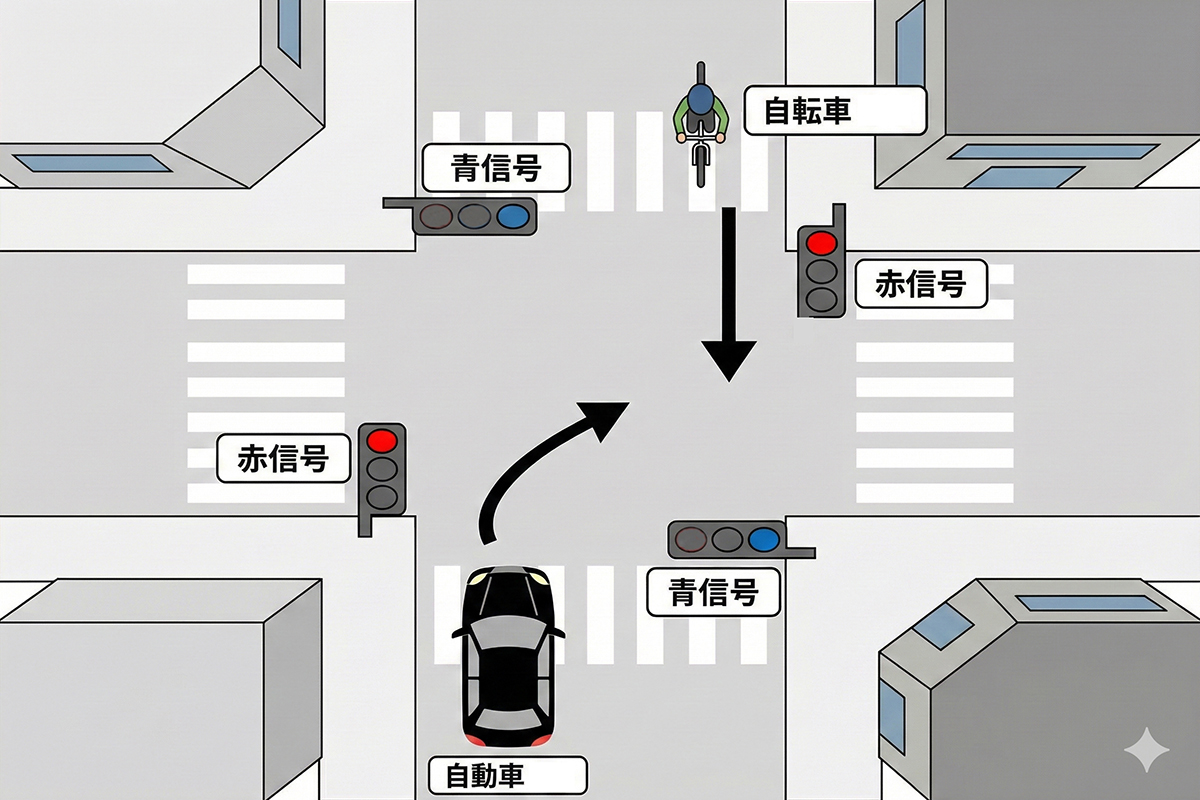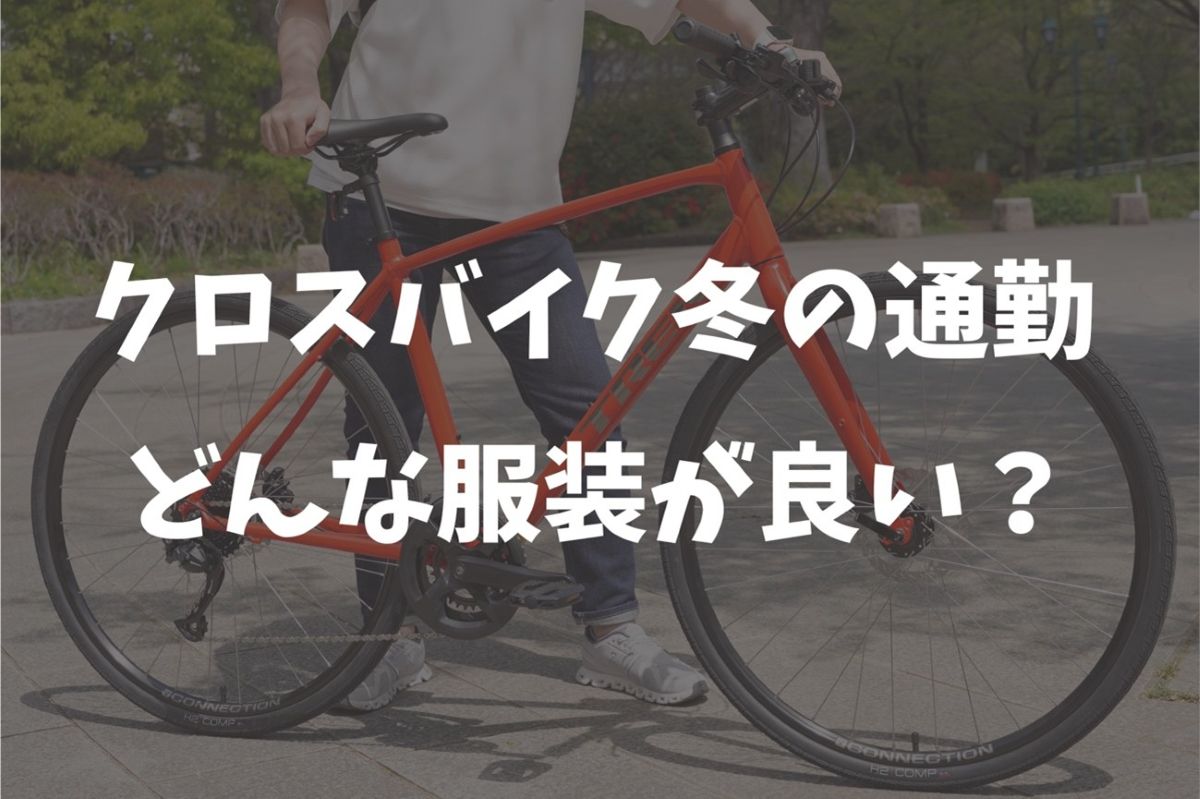ロードバイクは自動車と違って、なんといっても維持費が安い! のが特徴。自動車税や重量税はないし、燃料は不要だし、駐輪場も(自宅内に置くのであれば)無料。免許証の更新もないですし、車検もない…といった具合にとても経済的な乗り物です(※ただし、自転車保険には入っておきましょう!)
しかし、だからといって放ったらかしにしてはダメ。車検制度がないぶん、常に安全な状態で乗るには、オーナー本人の責任でメンテナンスし続けねばなりません。あと、どんな機材でもそうですが、使っていればパーツは劣化もしますし、摩耗もしていきます。よって定期的な交換も必要ですね。
「で、どのパーツが劣化しやすいの?」
「どれくらいの頻度で、どこの何を交換すべきなの?」
という疑問もあるでしょうから、その目安をお伝えします。
劣化しやすいパーツTOP2は「タイヤ」と「チェーン」
どんなパーツでも劣化はするものですが、その最たるものはタイヤとチェーン。走行中は常に動いていますので、摩耗も激しいわけですね。「タイヤは地面に接しているので摩耗するのは理解できるけど、なんでチェーンが劣化するの?」という気もするかもしれませんが、チェーンはかなりのパワーで引っ張られ続けているパーツですから、使っていると徐々に疲弊してくるのです。

長い距離を乗っていると、チェーンのひとコマずつをつないでいるピンが摩耗するなどの要因が重なって、チェーン全体が少しずつ“伸びて”きます。チェーンが伸び切ったままで走っていると、今度はカセットスプロケットの歯とうまく噛み合わなくなり、ギヤ側の劣化を早めてしまいます。
ちなみにチェーンの伸びは目視では確認できません。チェーンチェッカーという、チェーンの長さを計る物差しのようなツールがあるので、たまにショップに立ち寄った際とかに半年に1回くらい確認してもらうといいでしょう。
参考までに筆者の場合ですと、タイヤは1年で交換、チェーンは1年半で交換しています。それと、チェーンを交換するときはスプロケットも同時に交換するようにしています。つまり、チェーンとスプロケットの交換をセットで同時にやってしまうわけですね。理由は、チェーンとスプロケットの歯のかみ合わせを常にキレイに合わせておきたいからです。
このほかには、ブレーキシューの状態も時々チェックしておきましょう。ここも同様に消耗・劣化する部分です。またブレーキや変速のワイヤーも、長期間使用していると動きが鈍くなってくるので、趣味でそこそこ乗るのであれば、1年に1回を目安に交換すると快適に走れるでしょう。

「えー、同時交換だとお金がかかってしまう…」という場合は、メカニックさんに相談して決めるのがよいでしょう。ただ、ここはケチらないことを強くオススメします。
メンテナンスをしないと寿命は縮む
月に1000キロ以上走るような人でなければ、だいたいのパーツは1年くらいは問題なく使用できるはずです。ただこれは、ちゃんとメンテナンスするのが前提です。メンテナンスしないで放ったらかし状態にしていると、錆びたりカスがこびりついて固着したりして、摩耗スピードを早めてしまいます。とくにチェーンのメンテナンスはこまめにやったほうがよいでしょう。
■タイヤのメンテナンス
さほど神経質にならなくても大丈夫ですが、タイヤに異物が刺さっていないか、ひび割れしていないか等の目視チェックをたまにしてあげてください。異物が刺さりかけていたら奥に詰まる前にとってしまいましょう。
「たかが小さな石(砂)粒がなんの悪さをするのさ?」って思うかもしれませんが、これがタイヤの中に潜り込んでしまうと、徐々に奥へと入っていき、どこかのタイミングでチューブに到達し、パンクの原因となってしまうのです。信じられないかもしれませんが、本当です。

■チェーンのメンテナンス
チェーンはタイヤよりも頻繁にチェックしてほしいです。走り終わったらまず乾拭きするのを習慣に。チェーンオイルや路上で拾った砂を拭き取るのが目的です。汚いままだとチェーンの表面を劣化させます。拭くのは着なくなったTシャツとかでOK。
拭いてみるとわかりますが、走り終わったチェーンは真っ黒に汚れます。黒い汚れがほぼほぼなくなるまでゴシゴシ拭いてあげましょう。で、2回走ったら1回…くらいの目安でチェーンルブ(オイルですね)をさしてあげます。動きをなめらかにしてあげるためです。

「走るたびに乾拭き! 2回走ったらチェーンルブをさす!」を続ければチェーンの寿命をまっとうするまで使い続けられるでしょう。
タイヤ先端の摩耗具合で交換タイミングを知る
消耗するということは、いつか交換しなければならないわけですが、チェーンとかスプロケット同様、タイヤの交換タイミングもいつかやってきます。そろそろ交換だな…と把握できればパンクトラブルにも遭いにくいですからね。
タイヤの交換タイミングですが、「何キロ走ったら交換」とは断言がしにくいです。摩耗のしやすさは乗り手の体重や走り方、走行環境、またタイヤ自体のゴムの材質にも左右されますからね。また、レース用の軽いタイヤは走行面が薄く作られていたりして、あっという間に寿命が来ることもあります。
いずれにせよ、タイヤの接地面の摩耗具合を見ることで、交換時期を判断できます。摩耗しすぎたタイヤはパンクしやすいだけでなく、グリップ力も失われるので危険です。

交換タイミングのサインは「先端が平らになってきたら」です。目視と触診で平らになっていると感じたら、交換時期が近づいていると考えてください。

それ以外にも、タイヤ面に傷がついているとか、サイドにほつれが見えかけていたらこれも交換のサイン。命を乗せるモノなので、ぎりぎりまで使おうと考えるのではなく、「まだ行けるかな」くらいで交換するのがオススメです。
ディスクブレーキのブレーキパッドの交換目安
昨今シェアを伸ばしているディスクブレーキ式のロードバイクにお乗りの場合、ブレーキシューではなく、ブレーキパッドの交換がときどき必要です。シューと同じく、パッドも消耗品です。
ブレーキパッドはブレーキの本体部分の内側にセットされているので、ぱっと見だとどれくらい摩耗しているのか分かりにくいのですが、減りに気づかず乗り続けているとローター(円盤状のパーツ)を傷めてしまうことになりかねません。

ブレーキパッドの厚みは2mmそこそことかなり薄いです。で、使用できる範囲はシマノの場合で「0.5mm」まで。つまり、1.5mm削れてしまう前に交換しましょうという話です。
ただ、パッドはブレーキ本体の奥の方にあります。もともと薄いパッドが、さらに薄くなっていく様子を日常的にチェックするのは、初心者の方にはやや荷が重いでしょう。

さらに、油圧ディスクブレーキはブレーキレバーを握ったときの握りしろがブレーキパッドの摩耗に関係なく、「一定になる」よう設計されています。機能としてはありがたいのですが、逆に言うと、納車時とその後のレバーを引いたときの変化がほぼないので、パッドの減りに気が付きにくいという落とし穴があります。
パッドがすり減った状態でブレーキをかけ続けると、ブレーキローターも破損してしまいます。もし、摩耗具合の見極めに自信がなければ、自転車ショップでメカニックさんに診てもらうほうが確実です。
余談ですが、筆者も2020年の夏に人生初の油圧ディスクロードを買いました。リムブレーキより軽いタッチで強い制動力を出せるテクノロジーは素晴らしいものの、メンテナンスの難易度はリムブレーキよりも上がりました。いまだに戸惑うことが多々あるので、無理に自己解決しようとはせず、メンテナンス全般は信頼できるメカニックさんにお任せしています。メンテナンスの際は「SBAA PLUS」認定者在籍店などに預けるとより安心ですね。
ということで、ロードバイクの消耗品は
- ■ タイヤとチェーンが劣化しやすいと覚えておく
- ■ メンテナンスと清掃を習慣にする
- ■ タイヤ交換のサインを知る
- ■ (ディスクブレーキの車体に乗っている)ブレーキパッドの交換もする
を心がけてください。