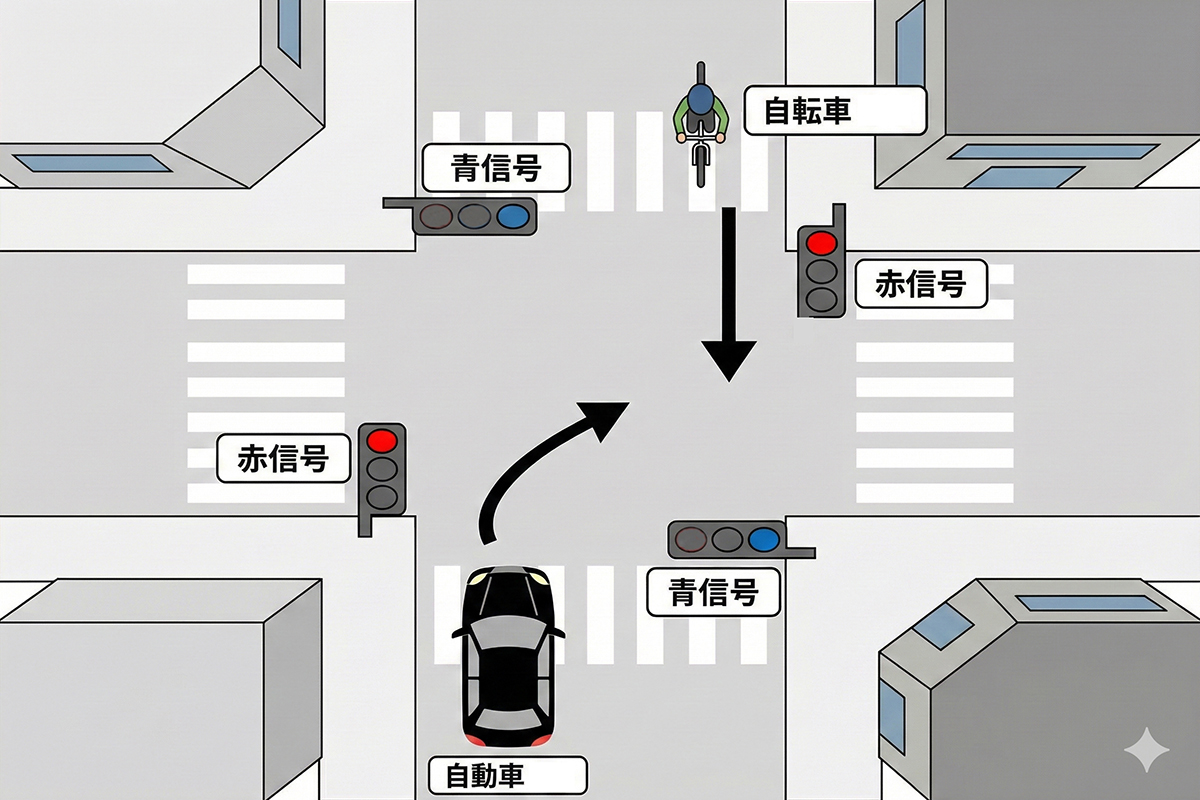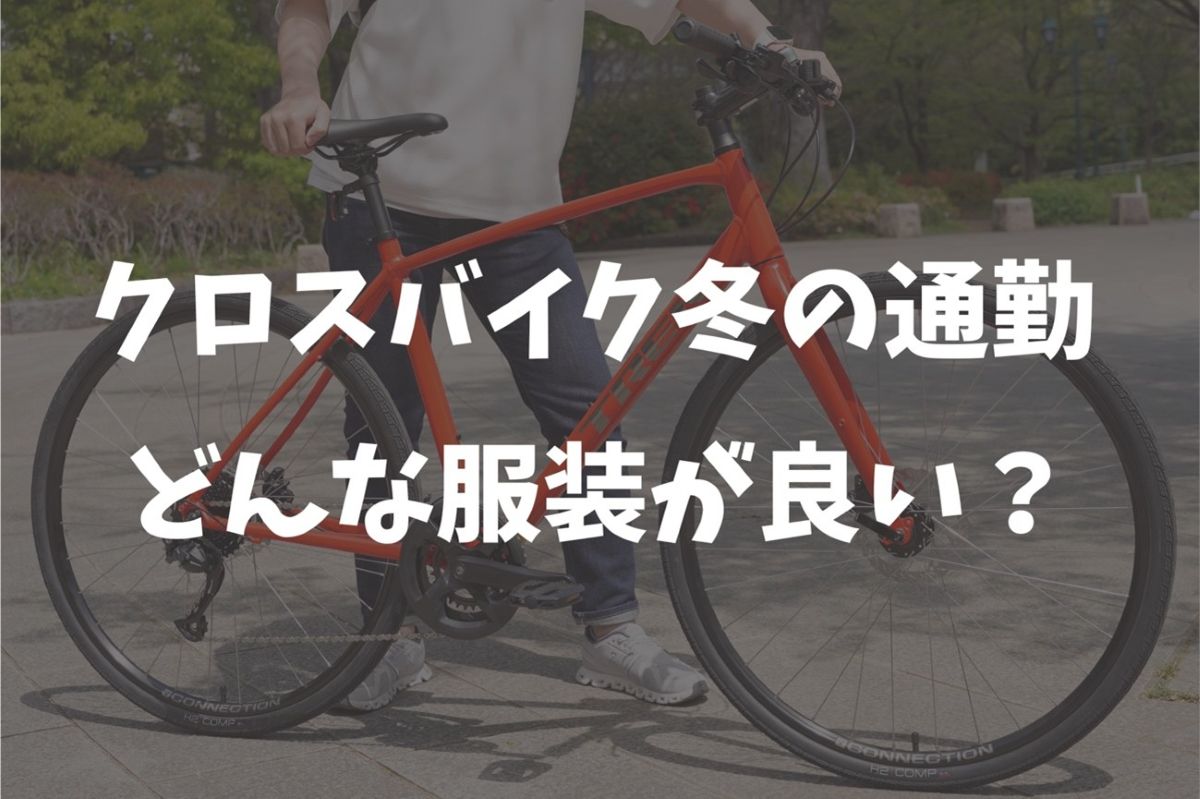1982年静岡県清水区生まれ。大学時代にサイクリング同好会でロードレースに出会い、卒業後に本格的に競技へ進む。JPROツアーチームや、UCIプロコンチネンタルチームなどに所属しで活躍。2014年の全日本選手権ロードレースで優勝。安定した走りと献身的なチームプレーで“ルーラー(平地を制する職人)”として知られる。2024年に現役を引退後は、指導者として活動。特に聴覚障害のあるデフサイクリストの育成に力を入れ、誰もが自転車を楽しめる環境づくりに取り組んでいる。
この人の記事一覧へ大学の同好会から競技の世界に進み、2014年の全日本選手権ロードで優勝した元プロロードレーサー、佐野淳哉さん。長年チームの中核として走り続け、引退後の現在は聴覚障害のある“デフ(※)サイクリスト”の指導にも力を入れています。そんな佐野さんに、自転車との出会いから現在の活動に至るまでのお話を伺いました。
※deaf=耳が聞こえない、聞こえにくい
自転車は“冒険の道具”だった
─佐野さんが自転車に興味を持ったきっかけは何だったのでしょうか?
最初に“自転車ってすごいな”と思ったのは、兄が愛知から静岡の実家まで自転車で帰ってきたときでした。200km近い距離ですよ。当時の僕にとって自転車は通学や遊びに行くための移動手段でしかなくて、そんな距離を走れるなんて想像もしていませんでした。
─その光景が、人生を変えた瞬間だったんですね
そうですね。「自転車って、こんなにも遠くに行けるんだ」と思ったんです。それまではただの乗り物だったのに、急に“冒険の相棒”に見えました。最初はトライアスロンに挑戦してみたい気持ちもありましたが、脚の不調で医師からランニングは控えたほうがいいと言われて、それなら自転車だけでやってみようと決めました。そこからどんどんのめり込んでいきましたね。
文化系からの転身、サイクリング同好会で見つけた“楽しさ”
─大学ではもともとオーケストラ部に入るつもりだったそうですね
そうなんです。高校ではコントラバスを弾いていて、大学でもそのまま続けるつもりでした。でも「何か違うな」と思って、意を決してサイクリング同好会に入ってみたんです。最初はレース志向もなく、ただ仲間と一緒に走るのが楽しかった。風を切って進む感覚が新鮮で、知らない場所まで自転車で行けることが嬉しかったですね。

── 最初のレース出場は、どんなきっかけだったんですか
友達に誘われて、軽い気持ちでクリテリウム(※)に出たんです。そしたら思いの外走れて、上位に入ったんですよ。そのときに「もしかして自分はやれるかもしれない」と感じて、少しずつ競技志向になっていきました。走るたびに課題が見つかって、それを超えるのが楽しくなっていった感じです。
※短い周回コースを何度も周回して争う自転車ロードレース
「ルーラー」として 地味でも誰かの役に立てる喜び
── プロの世界に進まれてから、走りのスタイルはどのように確立されたのでしょうか
僕は「ルーラー」(※)と呼ばれるタイプで、チームのために風を受けて展開を作る役割が多かったです。派手さはないですが、「逃げ」に乗ったり、仲間のために脚を使うことが性に合っていたんです。2014年に那須ブラーゼンで全日本選手権ロードで優勝を勝ち取れたのは、そうした地道な積み重ねがあったからだと思います。
※脚質の一つ。平地を一定のペースで走り続けることを得意とするタイプの選手
参照記事⇒『ロードレース選手の脚質を知る ルーラー、パンチャー、オールラウンダーとは』


─ 苦しい時期もあったのでは
もちろんありました。調子が上がらなかったり、チーム内での役割が変わったり、いろんなことがありました。でも不思議と「もう乗りたくない」と思ったことは一度もなかったですね。自転車は、自分でいろいろ工夫できる余白があるんです。走るルートを変える、時間をずらす、ギアを軽くする―そんなふうに少し変えるだけで、また新しい発見がある。だから、続けられるんだと思います。
「同じ道でも、毎回ちがう」走ることの発見
─佐野さんにとって“自転車の楽しさ”とは、どんなところにありますか?
同じ道を走っても、毎回見えるものが違うところです。季節や風の向き、気温、光の加減……ほんの少しの違いで景色が変わる。埼玉から東京へと流れる平凡な荒川の道を走るだけでも、春と冬ではまったく別の表情を見せてくれます。「今日は暑いな」「風が重いな」とか、そういう小さな変化が面白いです。
─現役時代とは、感じ方が変わりましたか?
大きく変わりましたね。選手時代はレースや練習で精一杯で、景色を楽しむ余裕なんてありませんでした。でもいまは、同じ場所を走っても「ここにこんな史跡があるんだ」と気づける。東海道を走ると、昔の宿場町の名残や石碑が残っていて、走るたびに小さな発見があります。スピードを競うだけが自転車じゃないと、改めて感じています。

「伝える立場」としての新しい挑戦
─現在はデフサイクリストの指導にも取り組まれているそうですが、どのようなきっかけがあったのでしょうか?
きっかけは偶然です。食堂でたまたま隣に座った方がデフチームの関係者で、話しかけてくださったんです。それがご縁で練習会に顔を出すようになりました。
2025年11月には「東京2025デフリンピック」という、「デフ(Deaf)」=「耳がきこえない・きこえにくい」アスリートを対象とした、4年に一度開催される国際総合スポーツ競技大会が日本で初めて開催されます。そこに出場する日本代表選手たちを指導しています。
─ 聴覚にハンディキャップがある選手を指導するのは、難しさもありますか?
声だけでは伝えにくい場面はあります。でも彼らは“見る力”がものすごく高いんです。手信号や姿勢の変化はもちろん、風の流れなども目で見てすべてを感じ取っている。僕らが“聞いて”判断していることを、彼らは“見て”理解しているんです。だから、やり方を工夫すれば十分にコミュニケーションが取れます。聞こえない部分を、“違う方法で分かり合う”感覚ですね。

─まさに“同じサイクリスト”としての信頼関係があるのですね
そうですね。前を走るときは大きく減速のサインを出したり、後方から伝わらないときは位置を入れ替えたり。互いに感覚を研ぎ澄ませて走る分、連帯感が強くなります。

自転車でつながる新しい世界
─最近では、タンデム自転車など誰もが楽しめる自転車のかたちも広がっていますね
そうですね。視覚障害のある方が後席に乗り、前に座る「パイロット」が操縦するタンデムは、スピード感や風の流れを共有できるのが魅力です。まずはタンデムで「自転車って楽しい」ということを感じてもらい、そこから自分で乗る世界につながっていけばいいと思います。
最近はハンドルにボタンをつけて、前後で簡単に合図できるようなデバイスもあります。テクノロジーを活用すれば、安全で快適に走れる機会がもっと増えていくと思います。誰が乗っても危なくない。そんな環境が整えば、自転車はもっと広がっていくはずです。
走るたび、新しい景色がある
─最後に、これから自転車を始めたいと考えている方に向けてメッセージをお願いします
難しく考えずに、まずは身近な道を走ってみてほしいです。同じコースでも、季節や時間帯が変わるだけでまったく違う景色になります。「昨日と違う風が吹いている」と気づけたら、それだけで自転車がもっと好きになると思います。

◇
大学の同好会から全日本チャンピオン、そして指導者へ。走るフィールドは変わっても、佐野淳哉さんの原点は変わりません。
「ペダルを回していれば、また新しい景色に出会える。それが自転車の一番の魅力だと思います」
走るたびに違う風景が広がり、新しい出会いが広がる。佐野淳哉さんの穏やかな笑顔が、その言葉を裏づけていました。
(聞き手・松尾 修作)